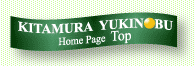
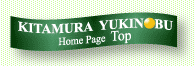 |
|
斎藤修 岩波書店 2014年6月18日刊 |
|
本書は環境、とりわけ森林の伐採とその保全のメカニズムをヨーロッパおよびアジアの比較経済史という観点から検討した、きわめて斬新な研究書である。 ただ、本書は単に環境史への経済学的アプローチというにとどまらない。現在、経済史学界で大きな潮流になりつつある、グローバル・ヒストリーの中で、東西経済の大分岐はいつであり、それ以前のアジアの経済をどう考えるかという大論争への、一つの実証的な視座を与えるものと考えるべきだろう。 著者が引用しているようにジャレド・ダイヤモンドの『文明崩壊』は、人口増加と森林乱伐による環境破壊によってもたらされたものであることが明示されている。同時に、近代以前であっても、森林保全を社会の仕組みとして機能させることに成功した例として、ティコピア島やニューギニア高地、徳川日本などを挙げている。 しかし、著者は日本が自然保護の意識が高く、自然との共存を一貫して実践してきたという見方はとらず、歴史を丁寧に繙けば、徳川前期と幕末維新期の二度にわたって、かなり深刻な森林荒廃を経験してきたことを明らかにしている。 とはいえ、近代以前に森林資源の崩壊という最悪の事態に陥らなかった理由の一つとして著者は、市場が機能していたこと、すなわち、木材が売れるなら植林をして売るという市場メカニズムが働いたことを指摘している。 また同時に、著者は消費需要に合わせた利益追求の結果として針葉樹林中心の植林政策が、大雨時には土砂崩れや下流域での氾濫などの被害を起こしやすくなっていること、そして花粉症の拡大やシカの異常繁殖などもその帰結であることを指摘し、儲かる樹種の植林に基礎をおく政策には見直しが必要であると警告している。著者は、その間の事情を踏まえたうえで、市場機構を信頼できるかどうかは、結局、市場を取り巻く政治的、社会的、制度的環境がどこまで安定的かに依存しており、その安定を維持するのは政府の役割であり、地域の多様で自発的な環境保全への取り組みであると結んでいる。 |