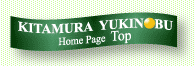
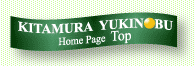 |
|
丸谷才一 講談社 2003年6月10日刊 |
|
本書は文学好き、言語問題に関心のある読者にはたまらなく面白い知的エンターテイメントである。 話はヒロインである国文学者杉安佐子を通して、松尾芭蕉の「奥の細道」の旅の真の目的は何であったかとか、紫式部の「源氏物語」に「輝く日の宮」という帖は実在したのかなど、文学史上の大きな謎に答えを与えることを軸にしながら、大学教授の生態や学会の実態についておもしろおかしく描いてみせたり、学会の重鎮とされる学者の権威を徹底的にこき下ろすといった趣向が大変効果的に使われた、いわば大人の遊びにあふれた内容となっている。 本書の第二の仕組みは、ヒロイン杉安佐子のラブアフェアーを藤原頼朝と紫式部の関係にオーバーラップさせて、最後に杉安佐子によって再現される「輝く日の宮」は安佐子自身の小説としても読めるということである。 しかしなんといっても本書の白眉は細部における言葉の遊びや文学上の知識にある。例えば、中学国語教科書には「奥の細道」ので出し「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり」という下りについて、「百代」を「ひゃくだい」と読むのか、「はくたい」と読むのか、という点を念入りに時代考証して、シェークスピアの「ハムレット」をエリザベス朝の英語で教えるべきかどうかという議論への展開は、まさに丸谷自身の関心のおもむくままの談論となっている。このような文学作品は丸谷才一でなければ書けないし、日本語でなければ楽しめない、知的ワンダーワールドとなっている。お奨めの一冊である。 |