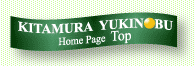
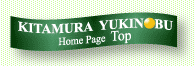 |
|
寺西重郎 岩波書店 2003年1月28日刊 |
|
日本の経済システムは大きな転換期に来ており、経済を新しい成長軌道に乗せるために様々な改革に着手し、将来の経済システムの青写真を提示することが危急の課題となっている。 本書は、そのような課題に答えようとして、著者がこれまで20年以上にわたって蓄積してきた金融史を中心とした地道な実証研究の上に、取りまとめられた本格的な日本経済システム論である。 本書の特色は経済システムを(1)外生的条件への適用、(2)政府と市場の関係、(3)経済・政治コストおよび価値規範、の3点から評価しようとする点にある。具体的には、明治大正経済システムを市場型システム、企業の大株主による支配と銀行の在来産業金融、中間組織としての地域経済圏の機能の3つの属性をもつものとして捉え、高度成長期経済システムを政府の経済への規制を中心とする広範な介入、経営者支配などの日本型企業システムと銀行を中心とする経済システムおよび原局・業界団体システムによる産業利害の調整によって特徴づけ、そこから将来の経済システムのあり方を探ろうとしている。 近年、歴史の一側面を切り取って、それが現状と似ているという極めて素朴な、そして歴史の流れ全体として見ればほとんど意味の無い比較に基づいて、政策議論を展開している人が多々見られるが、本書はそれらとは対極に立っている。そのアプローチは大きな流れとしては比較制度分析や比較歴史分析の系譜に位置づけられるものであろうが、広範な政治経済活動について具体的な統計数字を綿密に検討するという一橋大学経済研究所の数量経済史の伝統に則り、しかも最近の分析ツールも積極的に取り入れた研究となっている。 例えば、経済システムを形成する外生的条件をとってみても、明治大正経済システムではアジアにおいて唯一、先進国へのキャッチ・アップを目指す工業国であったこと、その結果として、二重構造問題を発生させ、比較生産費構造を無視したフルセット型の産業構造をもたらしたことなどが明らかにされている。さらに、そのシステムが次第にキャッチ・アップに伴う経済コストを増加させ、資本主義経済の矛盾を政府介入で解決しようという認識に移っていたことが説得的に述べられている。これは、単にケインズ的な思想が日本に入ってきたということではなく、より内在的な制度対応として、戦前は軍国主義に、戦後は修正資本主義的な政策思想に傾いてきたという点を制度分析の枠組みで説明しているのである。 歴史家がグランドセオリーに基づいて歴史を語らなくなってきた中で、本書は珍しく、大きなパースペクティブをもった研究書である。しかも、膨大な実証研究に裏打ちされた議論に基づいており、根拠のない観念論にはない説得力をもっている。 第5章の将来のシステム改革に対する考え方は、著者自らが「冷や汗もの」と書いているように、議論の余地が最も多い箇所であるが、このことは本書の価値を下げるものではなく、将来のより活発な議論のたたき台となるものとして受け止めたい。 |