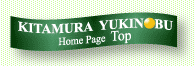
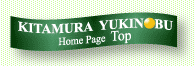 |
|
堀江敏幸 講談社 2001年2月8日刊 |
|
本書は昨年度(2001年)124回芥川賞を受賞した堀江敏幸の作品『熊の敷石』に加えて、『砂売りが通る』、『城址にて』の二本の短編を加えた作品集である。 『熊の敷石』というタイトルはラ・フォンテーヌの『寓話』第八巻第十話「熊と園芸愛好家」からとったものである。ラ・フォンテーヌの寓話はつぎのようなものである。孤独な熊と孤独な老人が山でばったり出会い、意気投合して一緒に暮らし始めた。熊の一番大切な仕事は老人が昼寝をしている間に、わづらわしい蝿を追い払うことであった。ある日、熟睡している老人の鼻先に一匹の蝿がとまり、なにをどうやっても追い払うことができなかった「忠実な蝿追い」は、ぜったいに捕まえてやると言うか言わぬか、「敷石をひとつ掴むと、それを思い切り投げつけ」、蝿もろとも老人の頭をかち割ってしまったといものである。その教訓は「かくして、推論は苦手でもすぐれた投げてである熊は、老人をその場で即死させたのだ。無知な友人ほど危険なものはない。賢い敵のほうが、ずっとましである。」ということであり、これが転じて、いらぬお節介を「熊の敷石」ということになったそうである。 小説『熊の敷石』の内容は、日本人の「ぼく」がユダヤ系フランス人のヤンのノルマンディの家を訪ね、そこで見聞きした事、思い出、その暮し向きを丹念に綴ったものである。とりたてて、事件があったり予想外の出来事が起こる訳ではない。小説は淡々と進行していく。本書のような小説の読みどころは、その細部(detail)にある。例えば、「林檎や梨の植えられた庭には、大時計を持ち込んだ老夫婦が使っていたパン焼き小屋が放置されていた。竈が壊れていて焼くのは無理だが、この近辺には町のパン屋まで足を運ばなくとも自宅の敷地内にある専用の小屋で、さきほどカフェで食べたような皮の固い田舎パンを焼くことのできる家が何軒かある。時間が経つと中身もかちかちになるのだが、そういうパンは包丁で細かく切ってスープに入れる。スープを飲むのではなく食べると表現するのは事実そのままを言っているわけで、実だくさんのスープがあれば、たしかに腹は満たされるのだった」という具合である。 そこで描かれている「ぼく」は『フランス語辞典』を書いたマクシミリアン=ポール=エミール・リトレの伝記の紹介文と部分訳をつくることが当面の仕事という人間であり、友人ヤンの撮った一枚の写真から、ナチ政権下でのユダヤ人問題へと話が発展し、ヤンの隣家の離婚した女性の盲目の子供のために作られた熊のぬいぐるみの目が×印で閉じられていることに気づいた「ぼく」の思考は、ラ・フォンテーヌの「熊の敷石」へと結びついていく。そして「もしかするとヤンにとって、この私は、ラ・フォンテーヌの熊みたいなものだったのではないか。・・・・実際には互いに互いの見えない蝿を叩きあっているのではないか。投げつけるべきものを取りちがえているのではないか」と自省する。 これは独自のスタイルを持った小説である。大きなストーリーが語られるのではなく、ひたすら、自分の思考の流れに従って物語りが進行していく。一種の教養小説ではあるが、とりたてて哲学的な主張を表に出しているわけではない。好き嫌いがはっきり出るスタイルだと思うが、私は本書を好ましく読んだ。 |