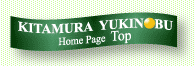
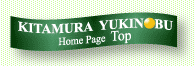 |
| ディヴィド・リス(Daivid Liss)(著) 松下祥子(訳) 早川書房 |
|
本書は2001年度アメリカ探偵作家クラブ(MWA)賞最優秀新人賞受賞作である。物語の舞台はロンドン、トピックは東インド会社などと同様の商事会社で、南アメリカのスペイン領諸国との貿易独占権を得て1711年に設立され、1718年には国王ジョージ一世が総裁となった南海会社(South Sea Company)の株式取引をめぐるスキャンダルである。 経済史に関心のある人ならご存知のように歴史上初の株式会社は東インド会社であり、南海会社もそれについで株式を発行している。因みにイングランド銀行が設立されたのが1694年で、南海会社が破綻したのが1720年である。 本書の扱っているのは破綻の前年1719年である。本書の主人公ユダヤ人のベンジャミン・ウィーヴァ−が実父の死の真相を探っていくプロセスにはミステリーの謎解き的要素は含まれているが、それにも増して面白いのは、当時の金融取引の多様性とそのいかがわしさである。まるで多様な生物がカンブリア紀に大爆発したのと同じように、政府発行の公債から、怪しげな事業計画への出資話(具体的にあった事業計画にはニシン漁、インドの煙草栽培、潜水艦建設、海水の淡水化計画、防弾チョッキ製造、蒸気エンジンの発明、柔軟性のある木材製造、食用犬の飼育などが含まれる)、宝くじまで様々な金融商品がほとんど無規制の中で取引されていたことが生き生きと描かれている。そしてそのような金融取引の担い手としてユダヤ人が重要な役割を演じており、同時に決してイングランドの人々には心よく受け入れられてはいなかったことは、シェークスピアの時代から変わりがなかったという点もよく描かれている。 ちなみに、一言でユダヤ人といってもイベリア半島出身のユダヤ人(これをセファルディーと呼ぶ)と東欧出身のユダヤ人(これをアシュケナージと呼ぶ)の間には習俗風習に違いがあり、当時、ロンドンで金融取引を担っていたユダヤ人は16世紀にイベリア半島からオランダに避難した(セファルディー)人たちである。ご存知のように1581年にはオランダは独立し、1602年に東インド会社を設立、1630年代には有名なチューリップバブルを引き起こしている。すなわち、彼らユダヤ人は経済取引のもつ魔力も恐ろしさも経験した上でロンドンに来た人たちであり、それがイングランドの無知な人々を食いものにしたという側面がある。(日本でもネズミ講的な組織が10年周期で発生するのは、過去の経験者がおなじことを形を変えてやっているからだという指摘がある)実際、17世紀のイギリスの金融革命はオランダ金融革命の影響下に発展したものであり、オランダ金融とさえ呼ばれていた。 また、株取引が株屋小路などにあるコーヒーハウスの一角で行われていたことは知られているが、それがどのような雰囲気であったのかということも本書はよく伝えてくれている。資本主義の創世期における混乱とその生き生きとした姿を知りたければ、本書はそのイメージを掴むには最適である。 南海会社の実際の破綻過程を簡単に知りたい人は『バブルの歴史』エドワード・チャンセラ−(著)山岡洋一(訳)(日経BP社、2000年刊)を読まれることをお勧めする。 |