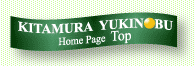
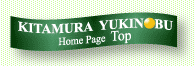 |
| ポール・ミルグロム、ジョン・ロバーツ(著) 奥野正寛、伊藤秀史、今井晴雄、西村理一、八木甫(訳) NTT出版 1997年11月10日刊 |
| 政府が行おうとしている行財政改革、金融ビッグバン等の構造改革はわが国の政治経済体制を21世紀に向けて一新することを意図している。改革の中心的課題は規制緩和と新組織・新制度のデザインである。 規制緩和の理論的根拠となるものは、市場メカニズムを通した調整が最も効率的であるという考え方である。この考え方に基づけば、政府は様々な規制や許認可制度、行政指導を廃止し、より一層市場中心の取引を奨励し、市場の監視機関として機能すべきだということになる。 他方、一部の経済学者は市場メカニズムを補完するものとしての組織や制度の役割を重視してきた。例えば、スタンフォード大学のケネス・アロー教授は名著『組織の限界』(村上泰亮訳、岩波書店)の中で、「組織の目的とは、多くの決定が、実際に成果をあげるためには多数の個人の参加を必要とするという事実を十分に生かそうとするところにある。…組織とは価格システムがうまく働かない状況のもとで、集団行動の利点を実現する手段なのである」(p.30)と述べている。アロー教授の指摘した組織・制度デザインの問題を敷衍したものが、スタンフォード大学ビジネス・スクールのミルグロム教授とロバーツ教授の著書『組織の経済学』である。 その内容はゲーム理論、情報の経済学、契約理論など現代経済学の分析手法を駆使しながら、組織内のモラル・ハザードの発生とそのコントロール、モラル・ハザード対策としてのインセンティブ契約、所有と財産権の問題、雇用政策と人的資源マネージメント、報酬とキャリア、企業財務とコーポレート・ガバナンス(企業統治)の構造など、主として企業組織の現実的な諸問題について論じたものである。ビジネススクールの教科書らしく、日本の事例も含めて様々な実例を用いており読みごたえがある。 本来、市場メカニズムの効率的活用を指向する規制緩和と組織デザインは相互に補完的な役割を果たすべきものであるが、これまでの政策議論では、規制緩和が先行し、組織デザインについてはようやくコーポレートガバナンスの議論が出てきた程度である。長年わが国の経済組織・制度の支柱と言われてきた、年功序列、終身雇用、メインバンクを軸にした間接金融などに取って代わるべき、新しい組織デザインはまだ見えてこない。こういう時には、日本より遥かに規制緩和の進んだアメリカで形成されてた組織が参考になる。本書は、アメリカにおける組織デザインの問題を文字通り教科書的に網羅したもので、新しい組織を考える際には最適の参考書となるだろう。 ただし、青木昌彦教授(スタンフォード大学)や奥野正寛教授(東京大学)らの研が示唆しているように、制度や組織自体が補完的なものであり、アメリカの制度・組織のいいとこどりをして、従来の日本的制度・組織の上にパッチワーク的に張り合わせようとしても上手く機能しない可能性が高い。 ここで重要なことは、21世紀を見据えた日本経済の基本理念を決めることでありその上で、組織の基本構造を策定していくことである。基本理念に関しては、野口悠紀雄教授(東京大学)が論じているように「失敗を認める社会」という考え方もあろうし、伊藤隆敏教授(一橋大学)が指摘するように「消費者主権社会」という考え方もあるろう。その上に構築すべき組織である法制度、社会保障制度、雇用慣行や賃金制度、企業制度、金融制度、税制などは相互に矛盾なく基本理念を支持するようにデザインされなければならない。言うまでもなく、組織は市場メカニズムにまかせても生まれてるものではなく、また規制緩和よりもはるかに広範な分野にまたがった作業である。組織デザインが緊急に要請されている現在、「本書が1990年代前半の日本経済の相対的に低いパフォーマンスの説明に有効」であり、「必要とされる改革の本質と範囲を理解する上で、本書で展開された考え方が有効だろう」(日本語版序文)という著者達のメッセージは決して誇大なセールス・トークではない。 |