
 |
|
●「ロンドン便り(2)」2003年2月28日 今日はアカデミックな話題について書きます。一つはアカデミックな交流に関してです。到着した翌日から1週間ほどはこの冬のAmerican Economic Associationのミーティングで面接を決めてきたPh.Dの学生のリクルートメントが行われていました。北米とジョブマーケットが連動していて、しかも双方向の行き来があるようです。北米のPh.Dがユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)に就職する反面、こちらのPh.Dも北米の一流大学、例えばノースウェスタン大学に就職するということが起こっています。この背後には、後で述べるように、研究者間の交流が緊密で、学会を通しての付き合いがあり、とりわけ研究雑誌の編集を通して意見の疎通、情報の交換が盛んに行われているということがあるようです。 最近の事情は判りませんが、オックスフォードやケンブリッジではここほど制度的にジョブマーケットの利用が行われているとは思えないので、これはロンドンという土地柄、計量経済学という共通性の高い分野ということもあるかもしれませんが、雇用体制がシステム化していることには驚かされました。 UCL
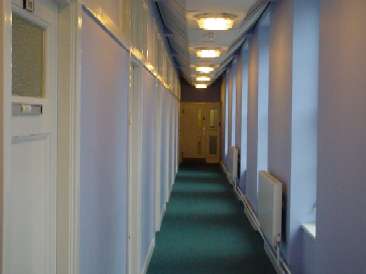
UCLには大きく分けて次のような経済領域の専門家が集まっています。計量経済学(特にミクロ計量経済学)、ゲーム理論や契約理論、産業組織論を中心としたミクロ経済学、開発経済学の3つです。ここの特徴は大きくまとめれば、ミクロ経済理論に基づいて数学的、計量的に経済問題を解決しようとしているということでしょうか。そのために、研究者の関心事が重なっており、おびただしい数の研究セミナーが連日のように開催されています。色々な分野の研究者が一同に参加しています。私が出たセミナーだけで、この2週間で8つありました。
すこし専門的になりますが、おもしろかったセミナーを紹介します。開発経済学では2月24日にベルギーからJean-Marie Baland が来てケニアの頼母子講(rotating savings and credit associations:roscas)がどのようにして維持可能になっているのかという実証研究を発表しました。これはマイクロファイナンスの分野で注目を集めているトピックで、ケニアのスラムに入って調査したというもので、極めて興味深い結果を出していました。同様の頼母子システムについては3月3日にMITのKaivan Munshiがインドのチェンナイ(旧マドラス)のChit Fund Associationの参加者が、政府の規制緩和でどのように内生的に参加額や期間を変更するのかを検討した論文を発表しました。これによると政策導入から2−3年で新たな均衡に収束することが示されていました。これも膨大なミクロデータを用いた実証研究です。 2月26日にはLSEのMartin Pesendorferが企業の参入ゲームの枠組みを実際のアメリカの5都市におけるホテル業への参入、退出データに当てはめた実証論文を発表しました。これは、ゲーム論、産業組織論とミクロ計量経済学がどのように融合できるかを試みた論文で、これまで見たことのないようなアプローチがとられていて極めて刺激的でした。要点は、計量経済学で必要とされるようなデータをてきるだけ削ぎ落として、離散選択情報だけから、実際の参入、退出をパラメトリックに推計できるかという試みです。ゲーム論ではかなりモデルを抽象化して、情報量もミクロ計量が持っているものよりはるかに少ない枠組みで分析しているので、そこに計量をできるだけ近づけようというものだと理解しました。これは、社会選択論でアローの一般不可能性定理が個人の二項選択のみから効用を組み立てているのと似ています。セミナーの参加者からもなぜもっと情報量を加えないのかという質問が計量経済学者の方から出ていましたし、私も一瞬そう考えたのですが、これはむしろ情報量を落とすことに関心があると気づき、問題の本質が見えたような気がしました。このようなゲーム論とミクロ計量経済学の交流は日本ではほとんど見られない中で、萌芽的な研究分野に触れたような気がしました。 2月27日にはパリからFrancis Kramarzが来て、アメリカとフランスの労働者の質と企業の業績の関係について、個別企業とそこで働く労働者のデータをマッチングさせた膨大なデータ(オリジナルの観察点は1600万)から、極めて刺激的な結果、すなわち、質の悪い労働者は業績のいい会社で働き、質のいい労働者は業績の悪い会社で働く傾向があるという実証結果を出していました。この論文の理論的基礎はベッカーの結婚のマッチングモデルであり、これについては考えたことがあったのでいっそう面白かったのですが、参加者の中には納得していいない人(特にCostas Meghir)もおり、そのやり取りも楽しめました。 このほかIFSでは毎週火曜日にランチセミナーがあり、IFSの若手を中心に彼らの研究結果を発表して、厳しい質問の中で鍛えられています。 これからも面白そうな発表が目白押しなので、またそれらの内容については報告します。 いま一つの話題は書籍に関してです。2月20日に用があって日帰りでオックスフォードに行ってきました。ブリティシュ・レールのオックスフォード駅から町に向かって歩き出すと、すぐのところにWaterfieldという古本屋があり、決して繁盛しているような店ではなかったのですが、1981年に初めてオックスフォードを訪れて以来、必ずよることにしていました。今回、それがオーディオショップに変わっていたので驚いていたところ、さらに歩いて、ブロードストリートに入り右手にあった古本屋までが姿を消し、やれやれと思いながらも気を取り直して、ブラックウェルの古本セクションを探すと、それがまた、3階の隅に押しやられ、その上、古本といっても、教科書や新刊書の在庫流れのようなものがほとんどで、実際に価値のある古書はほとんど見つからず、珍しく古本を手に入れることなくオックスフォードから帰ってくるはめになりました。 ロンドンではかつては他の名前でしたが今はWaterstoneと呼ばれる書店が各所にチェーン店を出し、LSE店にはかろうじて経済学の古書があり、Broomsbery店には歴史、哲学、政治、文学などの古書が置かれており、ここでは何冊か面白い本を見つけることができました。しかし、1980年代にはLSEにはMishanやBlaugがいて、かれらの蔵書から貴重な本がLSEの書店に出てきたものですが、今はそのような質の高い古書はほとんど見つかりません。同様に OxfordにはHicks, Harrod, G.D.H.Cole, T.S.Ashton, などがいて、彼らの蔵書から古書店に還流していたのですが、それも枯渇したのでしょうか、今は、カレッジの図書館から整理されて排出されてくる古書が中心になっており、当然ながら、本当に重要な本は出てきません。 これらの現象はイギリスだけの話ではないでしょうが、古書店回りを楽しみにしている者にとっては残念な限りです。その原因は書店の大型チェーン化、古書店のインターネットビジネス化で古書店が目抜き通りから消滅していること、学者の書籍ばなれなどが考えられます。あのオックスフォードのWaterfieldの屋根裏で午後いっぱいを古書を手にして、感激していた日々はもう戻ってこないのかと思うとやっぱり自分も年をとったのだという思いを強くしました。 北村行伸@London

|