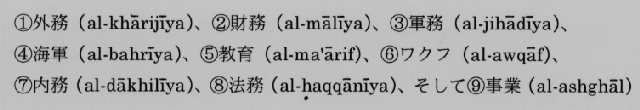
エジプトにおいて、「近代統計」を問題にしうるのは1882年以後の植民地行政下においてであるとして、以下、話を進めよう。ところで、「近代統計」が整備され、それに基づいて国家が有効に運営されるためには、次の三つの条件を必要とするであろう。
第一は、国家行政機構が「近代統計」を作成し、それに基づいて運営されうるほど近代化されることである。第二は、近代西欧的な統計学が統治のための学問・技術として受容されることである。そして第三は、近代西欧的な統計学を統治のために使いこなせるエジプト人の学者・官僚が育成されることである。
近代化とは、統治技術の側面を除けば、通常、行政機構の中央集権化を意味する。エジプトにおいても、例外ではない。このうち、地方行政の中央集権化については、先に言及したところから、ここでは、中央行政の中央集権化、具体的には、中央官庁、とりわけ省庁制と予算制度の整備について述べる。国民所得統計は国家運営の手段である以上、その作成主体は中央の省庁であり、それが有効に利用されるためには、合理的な予算制度の存在が不可欠だからである。
省庁制の整備 エジプトにおける内閣ならびに省庁制の歴史は、議会制の導入を計ったイスマイ−ルの治世(1863-79年)に遡れるとされている。しかし、王室財政と国家財政が未分化であった当時にあっては、内閣といい省庁といい、それはイスマイ−ルの諮問機関としての性格が強かった。
そのため、近代西欧にならった省庁制の成立というとき、それは、1876年の破産以降、エジプト財政が西欧列強の管理下に置かれ、国家財政が王室財政と切り離されるのを待たねばならない。つまり、1878年における9省庁の設置である。
このときに設置された9つの省庁とは、
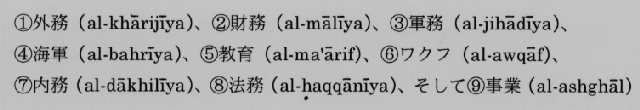
の各省庁である〔参考文献 (13) pp.13, 173〕。
以後、いくたびもの改組を経たが、一貫して、省庁の数は増えつづけた。ちなみに、エジプト革命後の1953年において、エジプトには15の省庁があった。それを列挙すれば、次の通りである。
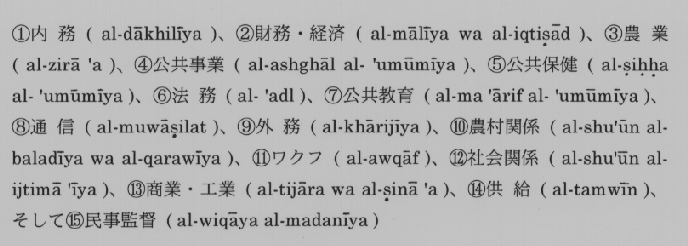
である〔参考文献(13) p.14〕。
予算制度の整備 当然予想されるように、エジプトにおける予算制度は、上記省庁制、エジプトにおける立憲君主制の展開と連動する形で整備されていった。その歴史を年表によって示すと、次のようになる〔参考文献(14) pp.1-13 〕。
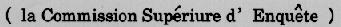 が設置される。
が設置される。
19世紀の前半、ムハンマド・アリ−は、国家の近代化過程において、西欧列強の内政干渉を警戒した。とりわけ、負債を口実とした西欧列強からの干渉を恐れ、財政面での独立に意を用いた。エジプトで最初の外債が発行されたのは、1862年のことである。
しかし、その反面、ムハンマド・アリ−は西欧の知識と技術を導入する点においては、貪欲であった。数多くの若い官吏、知識人が西欧に派遣され、また数多くのお雇い外人を招聘した。彼らが教師として赴任する、近代的な初等、中等教育機関、専門学校、高等教育機関も設立された。
こうして、エジプトには、外国人学者・官吏のアカデミック・サ−クルが形成されたが、時間の経過とともに、西欧への留学から帰国したエジプト人官吏、知識人が、このサ−クルに合流した。こうした外国人学者・官吏を中心としたアカデミック・サ−クルの代表が「エジプト学士院」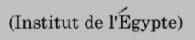 と「王立地理学協会」
と「王立地理学協会」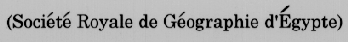 である。
である。
前者は、ナポレオンがエジプト遠征時(1798-1801年)にフランスの学士院にならって設立し、その後閉会していたが、1859年に再開された科学アカデミ−である。また後者は、1875年に設立され、非ヨ−ロッパ世界ではインドの王立地理学協会に次いで古い歴史をもつ地理学協会である。
1880年代以降、エジプトが西欧列強、とりわけ英の実質的な植民地となるにいたって、こうしたアカデミック・サ−クルは、政策立案のシンク・タンク的な役割までも担うようになり、ますます発展した。その代表格が、1909年に設立された「エジプト政治経済・統計・立法協会」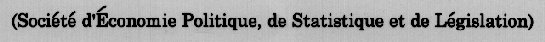 である。
である。
その紀要、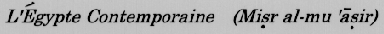 は現在にまで刊行されているが、そこには、国民所得関係統計を含む、多くの有益な統計的情報が盛られている。また、そこへの寄稿者のほとんどが、「エジプト学士院」や「王立地理学協会」の紀要の寄稿者でもあることが示すように、当時のアカデミック・サ−クルは、互いに連絡を取り合いながら活動していた。
は現在にまで刊行されているが、そこには、国民所得関係統計を含む、多くの有益な統計的情報が盛られている。また、そこへの寄稿者のほとんどが、「エジプト学士院」や「王立地理学協会」の紀要の寄稿者でもあることが示すように、当時のアカデミック・サ−クルは、互いに連絡を取り合いながら活動していた。
そして、このようなアカデミック・サ−クルのなかで、統計学が西欧における新しい学問として紹介されることになる。参考文献(6) (7) は統計学啓蒙の典型的な寄稿論文である。この二つは後に述べる統計局の局長経験者による論文であるが、このことが示すように、当時における統計学の紹介者のほとんどは、統計局の局長や顧問経験者であった。
さて、こうして紹介され、導入された統計学的手法も、それがエジプト社会に根づき、行政の実際に利用されるためには、エジプトにそれを理解し、操作しうる人的な受け皿がなくてはならない。つまり、統計学的手法を身につけた一群のエジプト人専門家や官吏の存在である。
こうしたエジプト人統計専門家の養成の必要性は、民族主義運動が高まり、エジプトの独立が日程にのぼるようになった両大戦間期には、切実なものとなった。かくして、1933年に、エジプトで最初の統計専門家養成コ−スが設置された。
つまり、この年、イギリスで統計学の学位を取った最初のエジプト人留学生、アブドゥルムニイム・シャ−フィイ− 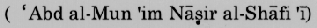 がエジプトに帰国し、商業高等学校(後のカイロ大学商学部)において、彼を教授とした統計学コ−ス(tadris)が開設されたのである〔参考文献 (8) p.487〕。
がエジプトに帰国し、商業高等学校(後のカイロ大学商学部)において、彼を教授とした統計学コ−ス(tadris)が開設されたのである〔参考文献 (8) p.487〕。
さらに、1946年には、当時にあって、大学院(修士、博士)課程をもつエジプトで唯一の統計教育機関である統計研究所(ma‘had)が開設され、カイロ大学商学部に付置された。この統計研究所は、1959年、大学機構の改組によって廃止され、新たにカイロ大学経済学部に統計部門が設置されたが、開設以来、廃止される1959年までの間に、この統計研究所からの卒業生は約150名に上った〔参考文献(8) p.488〕。
行政における統計的手法の導入は、当然のことながら、統計を専門に扱う機関や部局の設置をもたらした。その最初が、1905年、独立した部局として設置された統計・センサス局である。この部局は、財務省に付置された〔参考文献(8) p.490〕。
その後、この部局にならって、多くの省庁に統計部門が設置され、独自の統計を公表するようになる。時代は下るが、1957年の時点で、こうして独自に統計を公表していた省庁は、財務省のほか、次の12の省庁に上った。
つまり
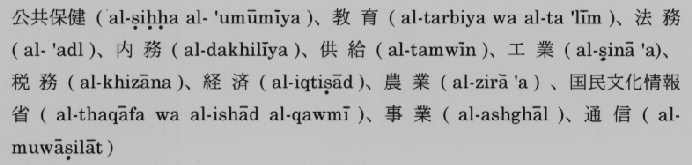
の各省庁である〔参考文献(8) pp.495-97〕。
その間、統計を専門に扱う政府機関の改組拡充が計られた。それを年表として整理すれば、以下のようになる。
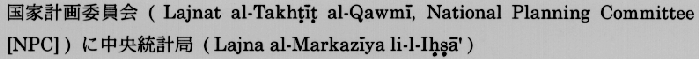 が付置される。
が付置される。