再論:70年代マルクス派搾取理論再検証
吉原直毅
一橋大学経済研究所
2004年5月2日 改訂2004年5月6日
1.
イントロダクション
私の「マルクス派搾取理論再検証――70年代転化論争の帰結――」(2001年7月,『経済研究』第52巻第3号)(以下、吉原(2001))に対する反論が、最近、松尾匡氏より『季刊経済理論』第41巻第1号(2004年4月)(以下、松尾(2004))において為されている。上記拙稿(吉原(2001))を詳細に検討していただいた松尾氏への謝意をここで表させていただくと同時に、松尾(2004)において展開された拙稿への批判的反論に対して、本稿においてできる限りの再反論を展開したいと思う。
松尾氏の吉原(2001)への批判は主に、以下の2点からなる。第一に、私が吉原(2001)において紹介した、「異なる消費選択の下でのマルクスの基本定理」の議論の中での、「均斉成長解が正の利潤率を持つときに個人的には負の搾取率をもつ労働者が存在する例」の数値例は間違っている。第二に、「一般化された商品搾取定理」に基づく、私の「マルクスの基本定理」の搾取理論的含意への批判は、マルクスの「人間主義的前提」に立つならば、妥当ではない。以上である。
これに対する私の本稿の反論は以下のように整理される。第一の松尾氏の指摘は正しい。しかし、これは単に数値例上での計算間違いに過ぎず、「異なる消費選択の下でのマルクスの基本定理」が成立するときに「均斉成長解が正の利潤率を持つときに個人的には負の搾取率をもつ労働者が存在する」ケースを一般に排除することはできない、という私の命題自体は依然として頑健である。そのことを、同じノイマン・モデルを使いながら、吉原(2001)での個人の需要関数とは異なる数値例を提示する事によって、論証する。第二の論点に関しては、松尾氏の「バナナの搾取=ナンセンス」論的な私への批判は、氏自身の「一般化された商品搾取定理」についての意味づけに基づくものであって、私自身がその定理から引き出している含意に対する批判ではない。私自身は、「一般化された商品搾取定理」について、「資本主義における利潤の源泉は、バナナが搾取されている事なり」、という類の解釈を取ったことはない。そして、松尾氏の「バナナの搾取=ナンセンス」論は、マルクスの「資本主義における利潤の唯一の源泉としての労働搾取」論の論証としては、「マルクスの基本定理」を位置づけることはできない、という私の議論そのものに関しての反論としては機能しない。以上が、私の回答である。
2. 「異なる消費選択の下でのマルクスの基本定理」再論
今、各労働者の消費需要関数が、個々に異なりうるフォンノイマン経済社会を考える。![]() でフォンノイマン経済体系を表し、それぞれ、
でフォンノイマン経済体系を表し、それぞれ、![]() は非負、非ゼロの
は非負、非ゼロの![]() 型産出行列、
型産出行列、![]() は非負、非ゼロの
は非負、非ゼロの![]() 型投入行列で、
型投入行列で、![]() は
は![]() 型の労働投入ベクトルでその成分はすべて正であるようなものであるとしよう。さらに行列
型の労働投入ベクトルでその成分はすべて正であるようなものであるとしよう。さらに行列![]() の各行は非負、非ゼロ
の各行は非負、非ゼロ![]() 次元ベクトルからなり、また、行列
次元ベクトルからなり、また、行列![]() の各列は非負、非ゼロ
の各列は非負、非ゼロ![]() 次元ベクトルからなるものとしよう。労働者の貨幣賃金率は1に基準化されていると考える。今、この社会に存在する労働者たちは、全員が同一の労働スキルを持ち、また互いに相異なりうる連続で単調増加、凸であって、かつホモセティックな消費選好を持っている。異なる消費選好に基づく労働者のタイプの集合を、
次元ベクトルからなるものとしよう。労働者の貨幣賃金率は1に基準化されていると考える。今、この社会に存在する労働者たちは、全員が同一の労働スキルを持ち、また互いに相異なりうる連続で単調増加、凸であって、かつホモセティックな消費選好を持っている。異なる消費選好に基づく労働者のタイプの集合を、![]() で表し、その一般的な要素を
で表し、その一般的な要素を![]() で表すことにしよう。したがって、価格
で表すことにしよう。したがって、価格![]() に対するタイプ
に対するタイプ![]() 労働者1個人が持つ消費需要ベクトルは
労働者1個人が持つ消費需要ベクトルは![]() で表すことができる。このとき、各タイプに関して
で表すことができる。このとき、各タイプに関して![]() が成立している。さらに、今、各産業工程
が成立している。さらに、今、各産業工程![]() によるタイプ
によるタイプ![]() 労働者たちの雇用労働量を
労働者たちの雇用労働量を![]() で表すとすれば、労働者階級全体での平均的消費需要ベクトルは、
で表すとすれば、労働者階級全体での平均的消費需要ベクトルは、
![]()
![]()
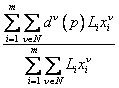
で定義されることになる。但し、![]() は
は![]() 型の非負ベクトルであり、これはタイプ
型の非負ベクトルであり、これはタイプ![]() 労働者たちの生産活動水準を記述するものである。ここで、
労働者たちの生産活動水準を記述するものである。ここで、![]() が成立する事に注意せよ。
が成立する事に注意せよ。
今、価格ベクトルの集合を![]() 次元単体
次元単体![]() で表す事にしよう。また、タイプ
で表す事にしよう。また、タイプ![]() 労働者たちの最大限供給可能な労働量、つまりタイプ
労働者たちの最大限供給可能な労働量、つまりタイプ![]() 労働者たちの労働賦存量の社会全体における総労働賦存量に占める割合を
労働者たちの労働賦存量の社会全体における総労働賦存量に占める割合を![]() で表す事にする。但し、
で表す事にする。但し、![]() であり、かつ
であり、かつ![]() となる。今、
となる。今、![]() となるタイプ
となるタイプ![]() 労働者たちの社会全体に供給可能な総労働賦存量を
労働者たちの社会全体に供給可能な総労働賦存量を![]() に基準化する。したがって、タイプ
に基準化する。したがって、タイプ![]() 労働者たちの実行可能な生産活動水準ベクトルの集合は、
労働者たちの実行可能な生産活動水準ベクトルの集合は、
![]()
で定義される。同様に、任意のタイプ![]() 労働者たちの実行可能な生産活動水準ベクトルの集合は、
労働者たちの実行可能な生産活動水準ベクトルの集合は、

で定義され、さらに労働者階級全体で実行可能な生産活動水準ベクトルの集合は、
![]()
で定義される。最後に、生産技術体系![]() に関して、以下の仮定を置く事とする:
に関して、以下の仮定を置く事とする:
仮定1: 純産出可能条件が満たされている:
![]()
![]()
![]() .
.
以上の設定の下で、1つのフォンノイマン経済環境がリスト
![]()
によって定められる。そのとき、フォンノイマン経済体系の均斉成長解は以下の条件を満たす、![]() である:
である:
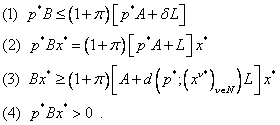
但しここで![]() である。
である。
定理1:仮定1を満たすフォンノイマン経済体系![]() において、均斉成長解が存在する。
において、均斉成長解が存在する。
上記の定理1より、条件(1)〜(4)式を満たす![]() が存在する事が、ここでのモデルの設定の下では保証される。しかし、ここで存在する均斉成長解が正の保証利潤率を持つものであるか否かは、尚、確定していない。均斉成長解が正の保証利潤率を持つための条件を確定するために、労働者階級の平均的搾取率について言及する必要がある。
が存在する事が、ここでのモデルの設定の下では保証される。しかし、ここで存在する均斉成長解が正の保証利潤率を持つものであるか否かは、尚、確定していない。均斉成長解が正の保証利潤率を持つための条件を確定するために、労働者階級の平均的搾取率について言及する必要がある。
労働者階級全体の平均消費需要ベクトルが![]() であるときの、労働者階級全体の平均的搾取率は、問題
であるときの、労働者階級全体の平均的搾取率は、問題
![]()
の解![]() によって定まる必要労働量を基にして
によって定まる必要労働量を基にして![]() と定義される。他方、各タイプ
と定義される。他方、各タイプ![]() の労働者たちの搾取率は、問題
の労働者たちの搾取率は、問題
![]()
の解![]() によって定まる必要労働量を基にして
によって定まる必要労働量を基にして![]() と定義される。このとき、以下の定理が成立する。
と定義される。このとき、以下の定理が成立する。
定理2 (異なる消費需要の下での一般化されたマルクスの基本定理 (吉原(1992))): 経済がフォンノイマン均斉成長解![]() の下にあるとしよう。このとき、
の下にあるとしよう。このとき、![]() と成る為の必要十分条件は
と成る為の必要十分条件は![]() である。
である。
上述の定理は、労働者個々人で相異なる消費需要を持ちうるようなノイマン経済における均斉成長解が正の利潤率を持つための必要十分条件を、社会の労働者全体からなる、商品への総需要ベクトルに基づく、労働者階級総体としての搾取率が正であることを明らかにしている。しかし、この定理では個々の労働者の搾取率が経済全体での平均利潤率とどう関わり合うかについては、何も言及していない。実際、以下の例で論証されるように、均斉成長解が正の利潤率を持つ、したがって、労働者階級総体としての搾取率が正である状況と、ある労働者たちの搾取率は負であるという状況とは、両立可能なのである。
例1 (均斉成長解が正の利潤率を持つときに個人的には負の搾取率をもつ労働者が存在する例):
フォンノイマン生産技術体系が![]() とする。今、この社会にはタイプ
とする。今、この社会にはタイプ![]() とタイプ
とタイプ![]() の2種類の互いに相異なる消費需要関数をもつ労働者たちが存在し、その総労働賦存量の比率は、タイプ
の2種類の互いに相異なる消費需要関数をもつ労働者たちが存在し、その総労働賦存量の比率は、タイプ![]() 労働者たちが1割、タイプ
労働者たちが1割、タイプ![]() 労働者たちが9割であるとする。すなわち、
労働者たちが9割であるとする。すなわち、![]()
![]() かつ
かつ![]() であるとする。今、価格が
であるとする。今、価格が![]() のときの1割いるタイプ
のときの1割いるタイプ![]() 労働者たちと9割いるタイプ
労働者たちと9割いるタイプ![]() 労働者たちの、所得1の下でのそれぞれの消費需要ベクトルを
労働者たちの、所得1の下でのそれぞれの消費需要ベクトルを![]()
![]() とする。
とする。
このとき、工程1及び工程2においてそれぞれ、タイプ![]() 労働を1割雇用し、タイプ
労働を1割雇用し、タイプ![]() 労働を9割雇用した場合の、社会の総雇用労働の平均的消費需要ベクトルは、
労働を9割雇用した場合の、社会の総雇用労働の平均的消費需要ベクトルは、
![]()
となる。したがって、
![]()
![]() 及び
及び![]()
が一つの均斉成長解を構成する。そのことを確認しよう。第一に、
![]()
かつ、
![]()
より、均斉成長解の条件(1)が等式で満たされている。よって条件(2)も、自動的に満たされる。次に、
![]()
かつ、
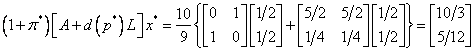
より、均斉成長解の条件(3)が不等式で満たされている。さらに均斉成長解の条件(4)が満たされている事も容易に確認できる。以上より、![]() は均斉成長解を構成する。
は均斉成長解を構成する。
ところで、このとき労働者階級の平均消費ベクトルは
![]()
であり、また、この経済では![]() が存在して、
が存在して、![]() と成る。したがって、
と成る。したがって、
![]()
より、![]() 。かくして、
。かくして、![]() より、確かに
より、確かに![]() であり、これはマルクスの基本定理と整合的な結論である。
であり、これはマルクスの基本定理と整合的な結論である。
他方、タイプ![]() 労働者の搾取率について見てみよう。タイプ
労働者の搾取率について見てみよう。タイプ ![]() 労働者の1労働日当たりの必要労働時間を導出する事は、以下の
労働者の1労働日当たりの必要労働時間を導出する事は、以下の
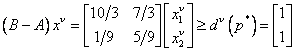
を満たす![]() の中で、
の中で、![]() が最小値となるベクトルを選ぶことに等しい。今、タイプ
が最小値となるベクトルを選ぶことに等しい。今、タイプ![]() 労働者の搾取率が非負になることとは、最小値に関して
労働者の搾取率が非負になることとは、最小値に関して![]() が成立することに他ならない。したがって、
が成立することに他ならない。したがって、![]() とならねばならない事を考慮して、上記不等式を整理すれば、結局、
とならねばならない事を考慮して、上記不等式を整理すれば、結局、![]() となる。これは、
となる。これは、![]() が成立しえない事を意味する。すなわち、
が成立しえない事を意味する。すなわち、![]() とならねばならない。これは
とならねばならない。これは![]() 、つまり、
、つまり、![]() を意味する。Q.E.D.
を意味する。Q.E.D.
以上の「正の利潤率の均斉成長解における労働者個人の負の搾取率の存在可能性」に関する数値例は、「均斉成長解における正の利潤率と任意の労働者個人の正の搾取率との同値関係についての一般不可能性命題」を証明するものに他ならない。上記の議論は、松尾氏の指摘の通り、確かに吉原(2001)における数値例自体は誤りがあったものの、そこで論じた「均斉成長解における正の利潤率と任意の労働者個人の正の搾取率との同値関係についての一般不可能性命題」自体は、結果的に頑健である事を確認させるものである。
上述の議論と吉原(2001)での議論の違いは、吉原(2001)においては消費選好の違いは各労働者が雇用される産業工程の違いに応じたものという制約された状況を想定していたのに対して、ここでは消費選好の違いは必ずしも雇用先の産業工程の違いに起因するとは限らない状況をも視野に入れている点である。その意味で、本稿における「異なる消費需要の下でのマルクスの基本定理」それ自体は、より広い想定を許したフォンノイマン経済モデルを前提にした可能性定理であるという点で、吉原(2001)におけるそれよりは強い定理であると言うことが可能である。他方、「均斉成長解における正の利潤率と任意の労働者個人の正の搾取率との同値関係についての一般不可能性命題」の方は、より広い想定を許した下で論証されているという点で、論理的には以前よりも弱い命題を意味する。[1]
以上の「正の利潤率の均斉成長解の存在可能性と任意の労働者個人の正の搾取率の同値関係の不可能性命題」の議論に対して、搾取率というのは資本家階級総体と労働者階級総体との間の階級的分配関係を表すマクロ的指標であって、個々の特定の労働者がどれだけ搾取されているかについてのミクロ的データに意味を与えるものではない、という反論が予想されよう。また、実際、階級全体として平均的労働が搾取されていようとも、個々の労働者の中には搾取の程度が極めて低い個人なり、場合によっては、むしろ搾取されているとは言えないような個人が存在していても、特にそのこと自体はマルクスの搾取論をなんら害するものではない、という見解は、一般的には説得的である。
しかし、ここでわれわれが論じている状況では、個々の労働者間での搾取率が正であるか負であるかの違いは、純粋に彼らの消費需要の違いによって生じているのであり、そのことこそが問題なのである。この状況では、個々の労働者の違いは消費選好だけであり、彼らの労働スキルも労働強度も労働時間も、貨幣賃金率も、まったく違いはないのである。つまりすべての個人はまったく同じ労働条件の下で雇用され、同じ賃金収入を得ているにも関わらず、個々人の消費選好の違いを反映した消費需要ベクトルの違いがあるが故に、労働者階級全体としては搾取率が正でありながら、ある個人の搾取率は負であったり正であったりするわけである。と言う事は、搾取率の決定要因は、労働者階級にとって客観的な資本主義的生産様式なり労働条件ばかりでなく、個々の労働者の主観的な消費財への好みの違いをも含むことを意味しよう。このことより、労働者たちの労働の成果の資本家たちによる取得の程度を表すと従来理解されてきた搾取率指標そのものの頑健性が疑われると言わざるを得ないであろう。
3. 「一般化された商品搾取定理」についての松尾氏の見解
吉原(2001)で展開した、「一般化された商品搾取定理」に基づく私の「マルクスの基本定理」批判に関しては、松尾氏は以下のような反論を展開している。第一に、松尾氏はレオンチェフ経済モデルにおける投下労働価値体系の双対的方程式と市場価格体系の双対的方程式を取り上げ、前者を経済系の外から人間が労働を投下し、経済系から人間のための純生産物を取り出す超歴史的事態として、そして後者を経済系の外から資本を投下して、経済系から剰余生産物を取り出す体系であり、人間も経済系の中で商品同様、再生産されるものとして扱われている、資本が主体となった物象化された体系であると解釈する。その解釈に基づいて、「マルクスの基本定理」とは前者の体系の視点に立って後者の事態を、「労働者階級が経済系の外から労働を投下して純生産物を取り出す。そのうちの一部は労働者達自身のものになるが、他の部分は労働者達の自由にはできず、資本家階級に貢がれる。それゆえその生産のために投下される分の労働は、労働者が資本家階級のために働いたことになる。」と解釈し、労働の搾取を見出すと言うわけである。この解釈のアナロジーで「一般化された商品搾取定理」が行っていることを解釈すればそれは、経済系の外からバナナを持ち込み、経済系からバナナのために純生産物を取り出す体系から資本が主体の物象化された体系を解釈することであり、バナナ仲間が身を投じて作り出された純生産物のうちに、バナナのため以外の目的で利用されるものが含まれる。それはバナナが搾取されている事態であることを意味すると言うわけである。そして、マルクスの「人間主義的前提」に立つならば、バナナのための純生産物を取り出す体系というのはナンセンスであり、したがって「バナナの搾取」という議論はナンセンスである、と批判されるわけである。
しかし、この批判は「一般化された商品搾取定理」への批判としては、妥当ではない。まず松尾氏の「マルクスの基本定理」解釈であるが、労働価値体系方程式の観点から価格体系方程式を解釈するというその議論自体は、マルクス自身の資本主義における利潤の唯一の源泉としての労働搾取論を、方程式解釈として当てはめているだけである。私の「一般化された商品搾取定理」を使った批判は、そもそもこうした解釈自体がマルクス主義の教義を共有する仲間内だけの議論としか通用しない、というものであった。「労働者階級が経済系の外から労働を投下して純生産物を取り出す。そのうちの一部は労働者達自身のものになるが、他の部分は労働者達の自由にはできず、資本家階級に貢がれる。それゆえその生産のために投下される分の労働は、労働者が資本家階級のために働いたことになる。」という解釈の論理的妥当性を主張するためには、正の利潤の存在と正の労働搾取との同値関係の主張だけでは不十分であり、少なくとも正の利潤の存在と同値関係にあるのは正の労働搾取だけであることまで主張する必要があろう。
「一般化された商品搾取定理」の成立は、この後者の主張が成り立たないことを示している点に意義があるのである。この定理を、「バナナの身になれば、利潤が存在するのはバナナが搾取されているからだ」という主張であると受け止めるのは確かにナンセンス以外の何者でもない。しかし、私自身はこの定理にそのような解釈を与えたことはないのである。人間社会における生産関係の一歴史的形態としての資本主義経済での労働搾取の含意と「バナナの搾取」とを並列に扱えない事くらいは十分に承知しているわけである。また、資本主義経済で労働搾取が存在しないという事を主張しているわけでもない。
「バナナの搾取」とは要するにこの経済の生産技術体系の下での正の剰余生産物生産可能性を、バナナをニュメレール財にして表現したものに他ならず、同じような解釈は労働をニュメレール財にして表現した場合にも成立するから、結局、「マルクスの基本定理」とは、正の利潤の存在の必要十分条件は正の剰余生産物生産可能性であるという自明な命題を、正の剰余生産物をある特定の財をニュメレール財に選んだ上で表現しているに過ぎないという解釈も可能である。このような複数の全く異なる含意が導出可能な定理に立脚している限り、正の利潤の唯一の源泉としての労働搾取の存在というマルクス命題の論証としては説得的でない、と言っているわけである。さらに、なぜ正の利潤が存在し、資本家に帰属するかについては、社会に賦存する物的資本財の相対的稀少性の存在と物的資本財の資本家階級による独占的所有の存在に基づく説明を展開してみせ、こうした議論も可能であることを示してきた。[2]
このように、松尾氏の批判は、「バナナの搾取」という定義それ自体に、労働の搾取とパラレルな解釈を提示して、そのナンセンスさを指摘するものであったが、そもそも私の「一般化された商品搾取定理」を用いた議論は、「バナナの搾取」の定義それ自体の解釈の独自性なり妥当性に依存するものではない。「バナナの搾取」の定義それ自体の解釈をどう与えようとも、「正の利潤の存在の必要十分条件は正の剰余生産物生産可能性であるという自明な命題を、正の剰余生産物をある特定の財をニュメレール財に選んだ上で表現しているに過ぎない」という「マルクスの基本定理」の位置づけ自体を否定する論理にはならない。その意味で彼の議論は、私の「一般化された商品搾取定理」を用いた議論に対する噛み合った反論として機能するものではないのである。
第二に、労働価値体系と価格体系から、「労働者階級が経済系の外から労働を投下して純生産物を取り出す。そのうちの一部は労働者達自身のものになるが、他の部分は労働者達の自由にはできず、資本家階級に貢がれる。それゆえその生産のために投下される分の労働は、労働者が資本家階級のために働いたことになる。」という読み込みをする松尾氏の解釈自体、マルクス主義の教義を共有しない人たちにとっては到底、説得的とは言い難いであろう。置塩・森嶋のマルクス経済モデルでは価格方程式体系の背景として、暗黙的に物的資本財に関して無所有の労働者階級と言われる人々と、物的資本財を占有している資本家階級の人々の存在を前提している。この前提が明示されて初めて、価格方程式体系において存在する賃金率と利潤率の相反関係が労働者階級と資本家階級の分配関係を同時に意味する事も了解される。
しかし、価格方程式体系それ自体はそうした階級間の分配関係のあり方とは論理的に独立なデータとして与えられている。したがって、直接的労働に寄与する個々人も物的資本財にアクセスできるような初期賦存状態であれば、必ずしも「そのうちの一部は労働者達自身のものになるが、他の部分は労働者達の自由にはできず、資本家階級に貢がれる。」という事態ばかりが生じるとは限らない。そういう事態が生ずる初期賦存状態を持つ経済モデルは資本主義経済モデルではない、と見なすのであれば、それは例えば「市場社会主義」の経済モデルであるという解釈も有り得るであろう。[3]そして「市場社会主義」をそれも「社会主義」という意味で、いわゆる資本主義社会におけるような「物象化された社会」とは原則的に区別されるという解釈にもし立つのであれば、市場価格方程式体系から直ちに「資本が主体となった物象化された体系」との読み込みを導き出すことは早計に過ぎよう。いずれにせよ、価格方程式体系それ自体のデータだけから資本主義経済に固有の「資本が主体となった物象化された体系」という特性を導き出すことは必ずしも出来ないのである。
さらに、投下労働価値体系では人間は体系外にあるのに対して、価格方程式体系では資本が体系外にあって、そこでは人間も労働力商品として体系内で再生産される、との「疎外論」的解釈も過剰な読み込みといえよう。そもそも人間社会の経済体系の役割の一つとして、人間自身の「再生産」をも位置づけることができると考えるならば、価格方程式体系それ自体において人間の体系内での再生産が表現されたとしても、それ自体からマルクス主義に特有な「疎外論」のストーリーを引き出すには無理があろう。現代の厚生経済学であれば、同じ価格方程式の双対体系モデルを使って、人間社会の「持続可能性問題」を論ずることも可能なのである。レオンチェフ経済モデルによる価格方程式双対体系および労働価値方程式双対体系は、マルクスの経済学体系の中のごく一部の議論を論証する役割を果たせるに過ぎず、豊穣なマルクスの理論体系の総体を議論するにはあまりにも貧弱な数理モデルでしかないことを、我々は肝に銘ずるべきである。
4. 結合生産モデルにおける松尾氏の労働価値の再定義に関して
松尾氏はさらに、結合生産のある経済モデルでの労働価値の彼自身による再定義(松尾(1997))を紹介し、その労働価値に基づく労働搾取の議論においては、それとアナロジカルに定義される「バナナの搾取」のナンセンスさが一層、際立つと論じている。その定義とは以下のように与えられる。今、労働者の財に関する消費選好を表す効用関数を![]() とする。これは各財について連続かつ単調増加な性質を持つものと仮定される。今、労働者の1労働日あたりの貨幣賃金1に対応する実質賃金バスケットが
とする。これは各財について連続かつ単調増加な性質を持つものと仮定される。今、労働者の1労働日あたりの貨幣賃金1に対応する実質賃金バスケットが![]() であるとしよう。この財ベクトル
であるとしよう。この財ベクトル![]() と少なくとも無差別な効用を与える任意の財ベクトルのうち、最小の労働投入で純生産可能な財ベクトルの労働投入量を、財ベクトル
と少なくとも無差別な効用を与える任意の財ベクトルのうち、最小の労働投入で純生産可能な財ベクトルの労働投入量を、財ベクトル![]() の労働価値とするのが、松尾(1997)の労働価値の再定義である。すなわち、最小化問題
の労働価値とするのが、松尾(1997)の労働価値の再定義である。すなわち、最小化問題
![]()
![]()
![]() ,
, ![]() :
: ![]()
の解の最小値![]() が財ベクトル
が財ベクトル![]() の労働価値となる。したがって、彼の労働搾取は
の労働価値となる。したがって、彼の労働搾取は![]() によって定義される事になる。
によって定義される事になる。
松尾氏はこの定義においては、労働者の効用関数を持ち出すことによって、労働者への財の配分が増える事が望ましいという、労働価値体系の「人間主義的立場」が一層、明らかになっていると述べる。さらに、この労働価値にアナロジカルにバナナ価値を定義するならば、その定義式ではバナナの効用関数が導入される事になるが、バナナの効用関数という概念のナンセンスさゆえに、バナナ価値及び「バナナの搾取」のナンセンスさも一層はっきりするだろうと言うわけである。その議論自体は、前節で述べたように、私の「マルクスの基本定理」批判への反論という体を無していない事に変わりは無い。
ここでは、この労働価値の再定義それ自体の妥当性についてまず検証する。松尾氏はこの再定義に基づく搾取の定義を前提にすれば、いわゆる劣等生産工程の存在によって生じる「搾取率ゼロの下での正の利潤の成立」という、結合生産モデルで生じる「マルクスの基本定理への反例」を解決する事が出来る事について言及している。しかしこの再定義では、労働者が財に関する消費選好として原点に強凸な形状の無差別曲線を持つような通常の場合であって、労働者の所得制約下での効用最大化の結果として財ベクトル![]() が与えられるような標準的な状況では、彼の1労働日あたり支払い労働量は彼の賃金所得によっては購入不可能な財ベクトルの労働価値として与えられたものとなる。支払い労働価値を実現する財ベクトルが実は彼に支払われた賃金収入の下では購入不可能であるという事は、そのような労働価値定義式に基づく搾取の定義の妥当性を疑わしいものとしよう。さらに、1労働日あたり必要労働価値を構成する財ベクトルを実際に購入する為には、労働者は既存の賃金収入1よりもより多くの収入を確保しなければならず、そして一度、その収入水準が保証されれば、彼はもっと高い効用をもたらす別の消費財ベクトルを選択でき、その財ベクトル純産出のための最小投下労働量は結局、1より大きくなってしまうだろう。
が与えられるような標準的な状況では、彼の1労働日あたり支払い労働量は彼の賃金所得によっては購入不可能な財ベクトルの労働価値として与えられたものとなる。支払い労働価値を実現する財ベクトルが実は彼に支払われた賃金収入の下では購入不可能であるという事は、そのような労働価値定義式に基づく搾取の定義の妥当性を疑わしいものとしよう。さらに、1労働日あたり必要労働価値を構成する財ベクトルを実際に購入する為には、労働者は既存の賃金収入1よりもより多くの収入を確保しなければならず、そして一度、その収入水準が保証されれば、彼はもっと高い効用をもたらす別の消費財ベクトルを選択でき、その財ベクトル純産出のための最小投下労働量は結局、1より大きくなってしまうだろう。
さらに労働者個人で与えられた所得の下での最適消費ベクトルは全く不変なままであっても、その背景にある効用関数は変化している場合を考えてみれば、同じ消費財ベクトルを同一の賃金収入の下で購入しておきながら、背景にもつ異なる無差別曲線の形状によって、労働者の搾取率が異なってくる、という事態も生じてしまう。つまり、労働者がどれだけ搾取されているかという問題は、労働者の客観的労働条件の問題ではなく、労働者の主観的な消費選好を表す無差別曲線の形状の違いによって生じてしまうという、マルクスの搾取理論としては受け入れがたい事態を生み出しうるのである。
以上の議論を、具体的な数理モデルを使いながら論証してみよう。
例2 (劣位生産工程を持つ結合生産経済体系におけるマルクスの基本定理への反例): 以下のようなフォンノイマン経済体系を考える:
![]() ,
, ![]() ,
, ![]() ,
, ![]() .
.
このとき、均斉成長解の集合は
![]()
![]()
となる。すなわち、均斉成長解においては常に![]() となる。他方、この経済における労働価値を計算すると、
となる。他方、この経済における労働価値を計算すると、
![]()
![]()
より、![]() であるので、搾取率は
であるので、搾取率は![]() となる。したがって、均斉成長解における保証利潤率が正である事と搾取率が正である事との同値性に関する森嶋(1974)の「一般化されたマルクスの基本定理」の頑健性は維持されている。しかし今、資本家の利潤最大化行動と整合的な競争均衡解を考えると、その集合は
となる。したがって、均斉成長解における保証利潤率が正である事と搾取率が正である事との同値性に関する森嶋(1974)の「一般化されたマルクスの基本定理」の頑健性は維持されている。しかし今、資本家の利潤最大化行動と整合的な競争均衡解を考えると、その集合は
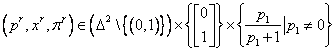
となる。つまり、競争均衡解では利潤率![]() は正である。したがって、正の利潤率とゼロの搾取率が両立するケースの存在が確認される。
Q.E.D.
は正である。したがって、正の利潤率とゼロの搾取率が両立するケースの存在が確認される。
Q.E.D.
以上のような「マルクスの基本定理への反例」は、純生産物生産可能性に関して、第一工程が第二工程に対して劣位生産工程となっている為に生じる。実際、Roemer(1980, 1981; Chapter 2)によって明らかにされたように、結合生産のある生産技術を持つ経済モデルにおいて劣位生産工程が存在しない事が、競争均衡解の下での正の利潤率と正の搾取率の同値関係が成立するための必要十分条件となるのである。
以上の帰結は、結合生産のある経済における労働価値の定義を森嶋(1974)のそれにしたがった場合の議論である。対して、森嶋(1974)の労働価値の定義とは異なる、松尾(1997)による労働価値の再定義に基づくと、上記のような劣位生産工程が存在する経済モデルでも、競争均衡解の下での正の利潤率と正の搾取率の同値関係が成立する事を確認できる。
例3:
今、例2のような結合生産経済であって、かつ、全ての労働者が同一の効用関数
![]()
を持つ経済環境を考えよう。そのとき、価格![]() のとき、労働者の実質賃金ベクトル
のとき、労働者の実質賃金ベクトル![]() は、1労働日あたりの賃金収入1の制約下での効用最大化行動の結果として労働者たちに合理的に選択される消費需要ベクトルとなる。さらに、このとき、
は、1労働日あたりの賃金収入1の制約下での効用最大化行動の結果として労働者たちに合理的に選択される消費需要ベクトルとなる。さらに、このとき、
![]() ,
, ![]() ,
, ![]()
は労働者の実質賃金ベクトル![]() を予算制約下での効用最大化解である消費需要ベクトルとして実現する唯一の競争均衡解を構成する。ここで
を予算制約下での効用最大化解である消費需要ベクトルとして実現する唯一の競争均衡解を構成する。ここで![]() である事に注意せよ。
である事に注意せよ。
以上の設定の下で、松尾(1997)の再定義による実質賃金ベクトル![]() の労働価値は以下のようにして求められる。ベクトル
の労働価値は以下のようにして求められる。ベクトル![]() そのものを労働投入を最小化するようにして純生産物として生産する際には、劣位生産工程である工程1のみが活動水準
そのものを労働投入を最小化するようにして純生産物として生産する際には、劣位生産工程である工程1のみが活動水準![]() で稼動される。しかし、
で稼動される。しかし、![]() と無差別な財ベクトルを純生産物として生産する為には、我々は優位生産工程である工程2のみを稼動させることでより効率的に生産活動を行うことが可能である。例えば、条件
と無差別な財ベクトルを純生産物として生産する為には、我々は優位生産工程である工程2のみを稼動させることでより効率的に生産活動を行うことが可能である。例えば、条件
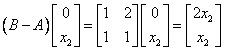 &
& ![]()
を満たす![]() を取れば、このときの対応する労働投入量
を取れば、このときの対応する労働投入量![]() こそ、松尾(1997)の労働価値の再定義に基づく、実質賃金ベクトル
こそ、松尾(1997)の労働価値の再定義に基づく、実質賃金ベクトル![]() の労働価値に他ならないのである。このとき、
の労働価値に他ならないのである。このとき、![]() であるから、松尾(1997)の労働価値の再定義に基づく労働搾取率は正値となり、したがって、この経済体系の下での正の利潤率をもつ競争均衡解の存在とマルクス主義的に整合的な結果である事が解る。
Q.E.D.
であるから、松尾(1997)の労働価値の再定義に基づく労働搾取率は正値となり、したがって、この経済体系の下での正の利潤率をもつ競争均衡解の存在とマルクス主義的に整合的な結果である事が解る。
Q.E.D.
以上の議論は、特定の効用関数の下で、実質賃金ベクトル![]() が所得制約下の効用最大化解として実現されるという設定の下で導かれたが、これらの設定を外したとしても尚、効用関数が各財に関して強単調増加である限り、正の利潤率をもつ競争均衡解の存在と松尾の労働価値の再定義に基づく正の搾取率の整合性自体は成立する。実際、各財に関して強単調増加な任意の効用関数
が所得制約下の効用最大化解として実現されるという設定の下で導かれたが、これらの設定を外したとしても尚、効用関数が各財に関して強単調増加である限り、正の利潤率をもつ競争均衡解の存在と松尾の労働価値の再定義に基づく正の搾取率の整合性自体は成立する。実際、各財に関して強単調増加な任意の効用関数![]() について、
について、![]() を満たす財ベクトル
を満たす財ベクトル![]() は、財ベクトル
は、財ベクトル![]() と原点
と原点![]() とを結ぶ線分と、ベクトル
とを結ぶ線分と、ベクトル![]() 上の無差別曲線との交点として決まる。そしてこの交点は、ベクトル
上の無差別曲線との交点として決まる。そしてこの交点は、ベクトル![]() 上の無差別曲線が厳密に右下がりの曲線である限り、労働投入量1のときのこの経済の純産出可能集合
上の無差別曲線が厳密に右下がりの曲線である限り、労働投入量1のときのこの経済の純産出可能集合
![]()
の内点になる。但し、記号![]() は、集合
は、集合![]() の凸包を意味する。財ベクトル
の凸包を意味する。財ベクトル![]() が労働投入量1のときの純産出可能集合の内点となる事は、この財ベクトルを第2工程のみで生産する際に必要な最小労働投入量が1より小さくなる事を意味するのである。[4]
が労働投入量1のときの純産出可能集合の内点となる事は、この財ベクトルを第2工程のみで生産する際に必要な最小労働投入量が1より小さくなる事を意味するのである。[4]
このように、森嶋(1974)の労働価値の定義に基づく場合に生ずる、劣位生産工程が存在する場合の「マルクスの基本定理への反例」は、松尾(1997)の労働価値の再定義に基づく搾取概念を採用するならば、うまく解消されるだろう事が解かる。[5] しかしミクロ経済学でもっとも標準的な設定の下では、松尾の労働価値の再定義はマルクスの搾取理論のモデルとして問題があることを以下のように確認できる。
労働者の効用関数が準凹であり、かつ実質賃金ベクトル![]() が所得制約下での効用最大化解であるような状況を考えてみよう。言うまでも無く、これはミクロ経済学でもっとも標準的なモデルの設定を意味する。例3で想定したような労働者の効用関数もこの状況を満たす一例である。その場合、ベクトル
が所得制約下での効用最大化解であるような状況を考えてみよう。言うまでも無く、これはミクロ経済学でもっとも標準的なモデルの設定を意味する。例3で想定したような労働者の効用関数もこの状況を満たす一例である。その場合、ベクトル![]() と無差別であって、第二生産工程だけを稼動する事で純生産物として生産可能な財ベクトルは
と無差別であって、第二生産工程だけを稼動する事で純生産物として生産可能な財ベクトルは![]() であり、これを純生産する最小労働量がベクトル
であり、これを純生産する最小労働量がベクトル![]() の労働価値
の労働価値![]() となるのであった。ところで、ベクトル
となるのであった。ところで、ベクトル![]() とは1労働日あたりの労働者の実質賃金ベクトルに他ならないから、マルクスの剰余価値論に基づけば、その労働価値とは彼の1労働日あたりの支払い労働量として解釈されるものでなければならない。しかし、ここでの労働価値の定義では、そのような解釈は不可能である。なぜならば、労働量
とは1労働日あたりの労働者の実質賃金ベクトルに他ならないから、マルクスの剰余価値論に基づけば、その労働価値とは彼の1労働日あたりの支払い労働量として解釈されるものでなければならない。しかし、ここでの労働価値の定義では、そのような解釈は不可能である。なぜならば、労働量![]() が体化されている財ベクトル
が体化されている財ベクトル![]() は、実際には労働者の賃金収入の下では購入不可能であるからである。実際、労働者の1労働日あたり貨幣賃金は1であるが、他方、競争均衡価格
は、実際には労働者の賃金収入の下では購入不可能であるからである。実際、労働者の1労働日あたり貨幣賃金は1であるが、他方、競争均衡価格![]() の下でベクトル
の下でベクトル![]() を購入するためには、
を購入するためには、![]() の所得が必要である。さらに、一度、労働者にベクトル
の所得が必要である。さらに、一度、労働者にベクトル![]() を購入可能とする所得が保証されるならば、そのときには労働者は競争均衡価格
を購入可能とする所得が保証されるならば、そのときには労働者は競争均衡価格![]() の下ではベクトル
の下ではベクトル![]() を選択はせず、ベクトル
を選択はせず、ベクトル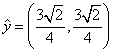 を選択するであろう。ベクトル
を選択するであろう。ベクトル![]() を純産出するために必要な最小投下労働量は明らかに1よりも大きくなる。以上の議論を総括すれば、労働者の賃金収入を越えた収入でなければ購入不可能なベクトル
を純産出するために必要な最小投下労働量は明らかに1よりも大きくなる。以上の議論を総括すれば、労働者の賃金収入を越えた収入でなければ購入不可能なベクトル![]() を純産出するために必要な最小投下労働量でもって、労働者の賃金収入に対応する支払い労働量と見なし得る理論的根拠は全く不確かであり、こうした労働価値の再定義に基づく搾取概念は、「マルクスの基本定理」を保持するために都合よく定義された労働価値概念であっても、マルクス主義の搾取概念それ自体には整合的であるとは言い難いのである。
を純産出するために必要な最小投下労働量でもって、労働者の賃金収入に対応する支払い労働量と見なし得る理論的根拠は全く不確かであり、こうした労働価値の再定義に基づく搾取概念は、「マルクスの基本定理」を保持するために都合よく定義された労働価値概念であっても、マルクス主義の搾取概念それ自体には整合的であるとは言い難いのである。
さらなる問題は、労働者の効用関数の形状が変わるに連れて、同じ1労働日あたりの同じ実質賃金ベクトルを前提したとしても、搾取率の値が変わってくるという点である。例えば、今、労働者の効用関数が![]() から、以下のような条件を満たす強単調増加かつ強凹な関数
から、以下のような条件を満たす強単調増加かつ強凹な関数![]() に変化したとしよう:
に変化したとしよう:
![]() &
& ![]()
![]()
![]()
![]()
![]() .
.
この場合も依然として、価格![]() の下でベクトル
の下でベクトル![]() は所得制約下の効用最大化解であるので、競争均衡解は以前と変わらない。しかし、いまやベクトル
は所得制約下の効用最大化解であるので、競争均衡解は以前と変わらない。しかし、いまやベクトル![]() の労働価値を決定する、
の労働価値を決定する、![]() の下で
の下で![]() と無差別な財ベクトル
と無差別な財ベクトル![]() は
は
![]()
となる事を確認できる。従って、対応するベクトル![]() を純生産可能とする最小労働量
を純生産可能とする最小労働量![]() は依然として1より小さい値であるものの、それは
は依然として1より小さい値であるものの、それは![]() よりは大きい値になる。したがって、効用関数が
よりは大きい値になる。したがって、効用関数が![]() へと変化する結果、以前と同じ労働時間であり、かつ、同じ賃金収入と同じ価格体系でかつ、同じ消費需要ベクトルであるにも関わらず、労働者の搾取率は低下するのである。客観的に全く同一の労働条件でありながら、その労働条件を評価する客観的指標であるはずの労働搾取率が、労働者の主観的な財への選好次第で変わりうる事を、この事態は意味している。そのような性質を持ってしまう「労働搾取率」が、マルクスの搾取理論の概念を発展させたものであると見なすのには無理があろう。となれば、問題は松尾流労働価値の再定義自体の妥当性が疑いの目を持って見なされざるを得ないのである。[6]
へと変化する結果、以前と同じ労働時間であり、かつ、同じ賃金収入と同じ価格体系でかつ、同じ消費需要ベクトルであるにも関わらず、労働者の搾取率は低下するのである。客観的に全く同一の労働条件でありながら、その労働条件を評価する客観的指標であるはずの労働搾取率が、労働者の主観的な財への選好次第で変わりうる事を、この事態は意味している。そのような性質を持ってしまう「労働搾取率」が、マルクスの搾取理論の概念を発展させたものであると見なすのには無理があろう。となれば、問題は松尾流労働価値の再定義自体の妥当性が疑いの目を持って見なされざるを得ないのである。[6]
5. 結語に代えて
前節で言及したように、労働者の効用関数を導入した労働価値の再定義に基づいて、松尾氏は「一般化された商品搾取定理」の議論を批判する。つまり、バナナの労働価値も松尾式労働価値の再定義にパラレルに再定義するならば、そこにはバナナの効用関数が導入される事になる。その結果、バナナ価値方程式の双対的体系が表現するのは、バナナによるバナナのための経済体系であり、それはマルクス主義の「人間主義的前提」とは相容れないものであり、そのような経済体系の下で導かれる「バナナの搾取」という議論はナンセンスである事が一層明瞭になる、と言うわけである。
この議論は、労働者の効用関数を導入した労働価値の再定義がマルクス主義の労働搾取の概念と整合的でない限り、説得性を持つとは言えない。しかし前節で検討したように、松尾式労働価値の再定義は、労働者の主観的な財への好み如何で、労働者の客観的な労働条件を評価する客観的指標としての労働搾取率が可変的となる、という問題点があった。また、その再定義は、そもそもマルクスの「支払い労働量」の概念とは両立しがたい、という問題点もあった。こうした問題点を考慮すれば、松尾式労働価値の再定義をマルクスの労働搾取概念の発展型と見なす事は困難であるという評価にたどり着く。となれば、労働者の効用関数を導入した労働価値の再定義を受容できない以上、バナナの効用関数のナンセンスさという批判自体も却下せざるを得ないだろう。
この批判に対して、労働者の効用関数を主観的な財への選好の表現ではなく、例えば労働者の「生活の豊かさ」を測定する何らかの客観的評価関数であると解釈するならば、少なくとも「労働者の主観的な財への好み如何で、労働者の客観的な労働条件を評価する客観的指標としての労働搾取率が可変的となる」という批判を免れる事は可能であろうという反論があるかもしれない。となれば、「バナナの効用関数のナンセンスさ」という「一般化された商品搾取定理」への批判ももはや適用できなくなる。バナナの効用関数もそれはいまやバナナという植物の主観的な選好の表現ではなく、バナナの生産技術条件の効率度を測定する何らかの客観的評価関数であると解釈されなければならないが、そのような指標を作る事は別に「人間主義的立場」と矛盾するものでもなんでもないだろう。資源を効率的に利用するための評価基準なり指標を作る事は、「人間主義的立場」の一側面といっても良いだろう。
実際、例えば環境資源問題を考える場合は石油価値などを考える事は、「人間主義的立場」から照らしても意味があろう。その場合の石油価値とは石油を最大限節約的に利用する生産活動を規定するものであり、その場合の石油の搾取とは、そのファースト・ベストの石油の利用の仕方に比して、実際の市場経済における生産活動で、どの程度、石油が無駄に利用されているかの指標として捉える事が可能だろう。現代の人間社会における持続可能性問題を考慮すれば、石油資源の利用の効率度を評価する「石油の搾取」指標は、極めて「人間主義的立場」に立つものであると言えよう。同様の事は、バナナ資源であっても、原理的には適用できる。バナナ資源の有効活用を評価するのもある意味、十分に「人間主義的立場」に立つものであると言えるであろう。
以上の議論は、バナナ価値概念の「人間主義的立場」から見た有効性についてのものであって、資本主義経済における正の利潤の源泉をどの生産要素に見出すかという、「マルクスの基本定理」の本来の含意に直接関わる議論ではない事に注意すべきである。その議論に関する限り、「一般化された商品搾取定理」の含意は、「資本主義経済における正の利潤の源泉は労働の搾取(ばかり)ではなく、バナナの搾取で(も)ある」という議論ではない事については、すでに2節で繰り返し指摘した通りである。松尾氏の「一般化された商品搾取定理」批判と「マルクスの基本定理」擁護論は、議論すべき問題を、我々が本来論じてきた「資本主義経済における正の利潤の源泉をどの生産要素に見出すか」というテーマから、「人間主義的立場」に基づく労働搾取およびバナナ搾取概念の意味づけの話へと摩り替えたものである、と言えなくもないのである。
数学付録 1
定理1の証明: 所与の市場価格![]() の下で、以下の最適化問題を定義しよう:
の下で、以下の最適化問題を定義しよう:
![]()
![]()
![]()
![]() (A1)
(A1)
行列![]() の各行は非負、非ゼロ
の各行は非負、非ゼロ![]() 次元ベクトルであることから、
次元ベクトルであることから、![]() であるので、上記の問題(A1)の解は一意に存在し、その解
であるので、上記の問題(A1)の解は一意に存在し、その解![]() は正値となる。
は正値となる。![]() を価格
を価格![]() の下での保証利潤率と呼ぶ。
の下での保証利潤率と呼ぶ。
所与の市場価格と対応する保証利潤率のペア![]() の下で、各タイプ
の下で、各タイプ![]() に関して、以下の最適化問題を考える:
に関して、以下の最適化問題を考える:
![]()
![]()
![]()
![]() (A2)
(A2)
ここで問題(A2)の解の集合を![]() で表す。集合
で表す。集合![]() は非空であり、ゼロの生産活動ベクトルを要素として含んでいる。
は非空であり、ゼロの生産活動ベクトルを要素として含んでいる。
次に、所与の市場価格と対応する保証利潤率のペア![]() の下で、各タイプ
の下で、各タイプ![]() に関して、任意に問題(A2)の解
に関して、任意に問題(A2)の解![]() を取り出して、プロファイル
を取り出して、プロファイル![]() を一つ構成すれば、対応する労働者階級の平均的消費需要関数
を一つ構成すれば、対応する労働者階級の平均的消費需要関数![]() を定義することができる。次に、以下の総超過需要対応
を定義することができる。次に、以下の総超過需要対応
![]()
を定義する。対応![]() は任意の価格
は任意の価格![]() に関して、非空、コンパクト凸値であり、かつ
に関して、非空、コンパクト凸値であり、かつ![]() 上において優半連続であることを確認することができる。さらに、任意の総超過需要ベクトル
上において優半連続であることを確認することができる。さらに、任意の総超過需要ベクトル![]() に関して、
に関して、![]() となることも確認できる。
となることも確認できる。
以上の議論より、Debreu (1959)の定理を適用すれば、ある価格ベクトル![]() 及び、ある超過需要ベクトル
及び、ある超過需要ベクトル![]() が存在して、
が存在して、![]() となることを確認できる。これは、ある生産活動水準ベクトルのプロファイル
となることを確認できる。これは、ある生産活動水準ベクトルのプロファイル![]() が存在して、
が存在して、
![]() かつ、
かつ、
![]()
となることを意味する。最後に![]() となることも容易に確認される。
Q.E.D.
となることも容易に確認される。
Q.E.D.
参照文献
Debreu, G. (1959):
Theory of Value, Wiley,
Morishima, M.
(1974): “Marx in the Light of Modern Economic Theory,” Econometrica 42,
pp.611-32.
Roemer, J. E.
(1980): “A General Equilibrium Approach to Marxian Economics,” Econometrica 48, pp.505-30.
Roemer, J. E.
(1981): Analytical Foundation of Marxian
Economic Theory,
Roemer, J. E.
(1994): A Future for Socialism,
Verso. (伊藤誠訳『これからの社会主義』青木書店, 1997年)
Roemer, J. E., and
Silvestre, J. (1989): “Public Ownership: Three Proposals for Resource
Allocation,” Department of Economics Working Paper No. 307,
Van Prijs, P.
(1992): “Competing Justification of Basic Income,” in Van Parijs ed., 1992, Arguing for Basic Income, Verso, pp.
3-43.
Van Prijs, P.
(1995): Real Freedom for All: What (If
Anything) Can Justify Capitalism?,
松尾匡 (1997):「価値論に関する最近の諸議論について」,『経済理論学会年報』第34集,
pp. 76-94.
松尾匡 (2002):「価値と再生産について最近の諸議論について」,『経済理論学会年報』第39集,
pp. 119-134.
松尾匡 (2004):「吉原直毅氏による『マルクスの基本定理』批判」,『季刊経済理論』第41巻第1号,
pp. 57-62.
吉原直毅 (1992):「現代経済学の観点からの搾取理論」,一橋大学大学院修士論文.
吉原直毅 (1998): 「搾取と階級の一般理論」,ISER
Discussion Paper,The
Institute of Social and Economic Research, Osaka University, No. 458.
吉原直毅 (1999): 「搾取と階級の一般理論」,高増明・松井暁編『アナリティカル・マルキシズム』 ナカニシヤ出版,pp.66-85.
吉原直毅 (2001): 「マルクス派搾取理論再検証――70年代転化論争の帰結――」『経済研究』第52巻第3号, pp. 253-268.
吉原直毅 (2002): 「榎原均『アナリティカル・マルキシズムへの疑問』へのコメント」, mimeo.
吉原直毅 (2004): 「マルクス主義と規範理論 (1)」, mimeo.