.gif)
3.国際資本移動と人的資本:クロスセクションデータによる分析
国の豊かさと国際資本移動の関係については Lucas (1990) の議論がわかりやすい。今、新古典派のマクロ生産関数 F (K, L ) を考えよう。ただし K と L はそれぞれ資本と労働の投入量をあらわし、等生産量曲線は原点に向かって凸とする。生産関数が一次同次とすると労働者一人当たり生産量を次式のように関数 f (・) で表すことができる。
.gif)
ただし y は一人当たり生産高、k は K/L を意味する。よく知られているようにこの時、資本の限界生産力 f '( k ) は資本労働比率 k の減少関数である。仮に国の間で生産技術に違いが無いとすれば、一人当たり生産高は k が大きいほど高くなる。したがって貧しい国ほど資本の限界生産力は高く資本が流入するはずである。例えば生産関数がコブ・ダグラス型で F ( K, L ) = K 0.4L 0.6 と表される場合には、一人当たり生産高が 1%低いことは、資本労働比率が 2.5%低く、資本の限界生産力が 1.5%高いことを意味する。
一人当たり生産高の国際格差は数十倍にのぼることは普通だから、以上の議論が正しいとすれば資本の限界生産力もそれ以上の規模で異なることになる。それなのになぜ豊かな国から貧しい国へ資本は大規模に流れないのか。これが Lucas (1990) が提起した謎である。
Lucas (1990) は人的資本を考慮すればこの謎に答えられると推測した。労働者一人当たりの生産関数が次式のように書けるとしよう。14
.gif)
ただし h は一人当たり人的資本蓄積量、k は労働を能率単位で測った資本労働比率をあらわす。(2)式からわかるように人的資本を考慮に入れると、各国間の一人当たり生産高格差は、(労働を能率単位で測った)資本労働比率の違いだけでなく人的資本の蓄積の違いによっても生じる。豊富な人的資本の蓄積によって一人当たり生産高が高い国の場合には、その国の(労働を能率単位で測った)資本労働比率が途上国よりもむしろ低く資本の限界生産力 f '( k )が高いといったこともありうるのである。
以上の議論は資本の投入量が瞬時に調整可能と仮定されているためそのままでは実証分析に使えない。この仮定のもとでは、資本移動が自由な 2国間で資本の限界生産力が異なる場合、その格差が無くなるまで瞬時のうちに資本が移動することになる。つまり、フローの資本移動量を理論的に説明することができない。
現実には資本の投入量を変化させるには調整費用を要し、急速に投入量を変化させようとすればするほど、調整費用は逓増すると考えられる。このような Uzawa (1969) タイプの調整費用関数を仮定すれば、フローの資本移動量を理論モデルで説明することができる。
よく知られているように経常収支の不均衡は、資本移転を除けば海外に対する債権の純増に等しい。従って最も広い意味での資本移動の純額は、その国の経常収支で捉えることができる。経済発展の程度と経常収支の関係については、これまでにも経常収支の発展段階説として Onitsuka (1974)、Blanchard (1983)、鬼塚 (1985)、Blanchard and Fischer (1989)、Eichengreen (1991)、須田 (1992) 等の研究が行われてきた。以下では Blanchard、Eichengreen、Blanchard and Fischer 等の提示したモデルに人的資本を導入することにより、Lucas のアイデアを実証可能な形に定式化する。
世界には一財しか無いものとし、資本は自由に国際移動できるが労働は国際移動しないとする。分析の対象とする国は小国であり一定の世界実質金利 r に直面しているとすると、企業の最適資本蓄積行動と家計の時間を通じた最適消費行動を分離して解くことができる。単純化のため人口は一定とし、一人当たり人的資本量 h も与件とする。h が内生的に蓄積される場合についてはのちにふれる。この国の代表的企業はネットキャッシュフロー流列の割引現在価値の総和を最大にするように労働投入量および投資額を決めると考えられる。この時、資本蓄積の経路は以下の最適化問題の解として得られる。
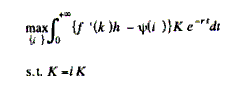
ただし記号・は変化率を表す。また ψ(i) K は資本を i の成長率で蓄積するのに要する投資額を表す。上式のうちマクロ経済において決まる k の経路は個別企業の意思決定において与件である。Uzawa (1969) に従い、ψ'(・)>0、ψ"(・)>0、ψ(0)=0、ψ'(0)=1 を仮定する。これは急速に資本を蓄積しようとするほど、資本増加一単位あたりの投資費用が上昇することを意味する。
Blanchard and Fischer (1989) が分かりやすく示しているように、企業の最適行動のもとでマクロ経済における k の動学経路は次式に従う。
.gif)
ただし q は資本ストックの帰属価格を表す。上式から、k の経路は長期均衡値 k * に収束する事がわかる。ただし k * は次式で規定される。
.gif)
詳しい議論は Blanchard and Fischer (1989) に譲るが、長期均衡の近傍で体系を線形近似すると、k の動学式は次式で表される。
.gif)
ただし α は正の定数である。この式は(労働を能率単位で測った)資本労働比率 k が長期均衡値 k * に比べ小さいほど、資本蓄積が活発であることを意味する。当該国の一人当たり生産額から一人当たり投資額を引いた値 f (k )h −ψ(i)k h を純生産と呼べば、k が小さいほど純生産は少なくなる。
われわれのモデルでは純生産と海外からの要素所得受取の和と自国民の消費の差が経常収支に等しい。したがって経常収支を分析するには家計の消費行動を考慮する必要がある。当該国の代表的家計の直面する最適消費問題は次のように書けるとする。
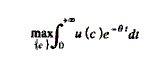
だたし次の予算制約に従う。
.gif)
時間選好率 θ は世界金利 r に等しく、瞬時効用関数は下方に強凹とする。z は一人当たりの対外純資産を表す。予算制約式右辺の純生産は代表的家計が配当および賃金として受け取る所得の和である。15 良く知られているようにこの時、家計の消費関数は次式で与えられる。
.gif)
ただし x は自国家計の人的資本を含めた一人当たり総資産を表し、初期時点の x は次式で定義される。
.gif)
時間選好率が世界金利に等しいと仮定しているため、最適消費行動のもとで x は一定に保たれる。(9)、(10)式は、純生産が将来増加すると予想される場合には、現在の消費水準は高くなることを意味する。
当該国の経常収支黒字対 GDP 比は (f (k )h −ψ(i)k h +r z −c )/f (k )h で与えられる。
(8) 式が示すように、(労働を能率単位で測った)資本労働比率 k が低いほど純生産は少ない。一方、k が低いほど資本蓄積が活発で将来純生産の増加が予想されるから、消費水準は高くなる。したがって、k が低いほど経常収支赤字は大きくなる。一人当たり GDP、f (k )h が等しい2つの国では、人的資本 h が大きい国の方が資本労働比率 k が低いはずである。そのような国は経常収支赤字が大きいことがわかった。
以上の結果を要約しよう。われわれの仮定のもとでは、人的資本 h 、一人当たり GDP、対外純資産 z の3つが与えられれば、理論モデルから経常収支対 GDP 比がどのような値になるか答えることができる。それぞれ他の2つを与件とするとき、人的資本 h が高いほど、一人当たり GDP が低いほど、また対外純資産が少ないほど、経常収支赤字は大きくなる。
これまで与件としてきた人的資本は、教育投資のコストと教育による賃金上昇の比較考量により決定される内生変数と考えるべきかも知れない。人的資本の蓄積についても実物資本と同様の投資関数を想定することにより、人的資本を内生化することは難しくない。その場合、他の条件は同一として人的資本が稀少な国では人的資本の帰属価格が高いため、教育投資が活発になる。教育投資は国内の純生産を減らすから、経常収支の赤字要因である。したがって、人的資本と経常収支の関係に関するわれわれの結論は逆になる可能性がある。結局、人的資本の大小が経常収支に与える影響は物的投資と教育投資の相対的な規模で決まる。前者が後者より格段に大きい経済では、これまでの分析と同じく豊富な人的資本は経常収支赤字をもたらす。
1960年以降について初期時点の人的資本および一人当たり GDP とその後の経常収支対 GDP 比の関係を検証した結果が表1にまとめてある。アジア諸国の経済成長等によって、データが利用できる 35年間の間に各国の相対的な豊かさは大きく変動した。そこで、ラテンアメリカ諸国を中心とする累積債務問題により国際資本移動の形態が変わった1980年代初頭を境に、1981年までとそれ以降に分けて推定を行った。なお、期間を分けない推定も試みたが、主な結果は変わらなかった。理論的には人的資本および一人当たり GDP に加えて、初期時点における対外純資産も経常収支対 GDP 比の決定要因と考えられる。しかしデータの制約のため、この変数は説明変数に加えることができなかった。
推定にあたっては先進国を含めデータの利用できるすべての国を対象とした。なお、各国への資本流入のうち途上国の外国政府・公的機関からの借入は、援助の性格が強く、民間部門からの借入とは決定要因が異なっていると考えられる。そこで、外国政府・公的機関からの借入データが利用できる81年以降の推定では被説明変数を(経常収支−外国政府・公的機関からのネットの借入)/GDP の期中平均値とした推定も試みた。推定にあたっては、OLS と不均一分散を考慮して、各国の初期時点におけるGDPで加重した最小二乗法の両方を試みた。
表1−aは各国の各年の経常収支対 GDP 比の1960−81年に関する平均値(%)を被説明変数とし1960年の一人当たり GDP と人的資本を説明変数(ともに対数値)とした回帰分析、表1−bは各国の各年の(経常収支−外国政府・公的機関からのネットの借入)対 GDP 比の1982−95年に関する平均値(%)を被説明変数とし、1982年の一人当たり GDP と人的資本を説明変数(ともに対数値)とした回帰分析のそれぞれ結果である。82年以降について経常収支対 GDP 比の期中平均値を被説明変数とした推定も試みたが、主な結果は変わらなかった。
データの詳細と出所は以下のとおりである。
経常収支/GDP:分母は各国通貨建名目 GDP を年平均の市場レートでドル換算した値。
各変数は IMF、International Financial Statistics各号より得た。
外国政府・公的機関からのネットの借入:World Bank、World Debt Table と Development Finance 各号より。世銀にデータの無い先進国についてはゼロとして扱った。
一人当たり GDP:Penn World Table 5.6 の購買力平価で換算した一人当たり実質 GDP(1985年国際価格)。詳しくは Summers and Heston (1991) 参照。
人的資本:Penn World Table 5.6 より得た25才以上人口の平均教育年数。5年毎のデータしかないため、82−95年の推定には80年のデータを使った。
表1にまとめたように、2つの期間ともに予想どおり、初期時点の一人当たり GDP の係数は正、人的資本の係数は負との結果を得た。また、多くの場合について推定された係数は有意であった。特に1982年以降の期間に関する推定では、人的資本の係数は大きく、また一人当たり GDP のみを説明変数とする単回帰の場合と比べて人的資本を加えることで決定係数がかなり上昇している。例えば(6)式の結果は、一人当たり GDP が 10%低いと(経常収支−外国政府・公的機関からのネットの借入)対 GDP 比が 0.3%減少する(その分民間ベースの資本流入が増加する)のに対し、25才以上人口の平均教育年数が 10%高いと、(経常収支−外国政府・公的機関からのネットの借入)対 GDP 比が 0.23%減少することを意味する。近年の国際資本移動を理解する上で、人的資本の重要性が高いと言えよう。この推定結果はまた、途上国が対内投資を促進するうえで人的資本の蓄積が有効な手段であることを意味している。
なお、図3で見たとおり、1980年代初めの累積債務問題以後、途上国への資本移動において直接投資の占める比重が高まっている。多国籍企業の立地選択においては、賃金水準だけでなく労働者の質も主要な決定要因と考えられる。1982年以降に関する推定結果はこのような資本移動形態の変化を反映しているのかも知れない。
なお、クロス・カントリーではなく、国内の地域データを使っても地域別の豊かさと資本移動の間の関係が分析できる。例えば日本の府県データを使った、岳 (1995、1996) は、一人あたり県内総生産と貯蓄・投資差額の間には強い負の相関が有るものの、これは政府が所得・資本移転を行っているためであり、民間の貯蓄・投資差額に限ると相関はないとの結果を得ている。ただし一国内では資本移動の規制が無い、特化が顕著、交易が活発、16 生産技術が比較的均質、労働が自由に移動できる、などクロスカントリーと条件が違うことに注意する必要がある。また府県別の経常余剰データは財・サービスのクロスボーダー取引のデータが十分でないため誤差が大きい危険があることに注意する必要がある。